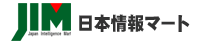社員へのプレゼントは給与課税されるのか? 福利厚生費との境界線
1 社員へのプレゼントは福利厚生か給与か?
経営者なら、「毎日、頑張って働いている社員への感謝の気持ちを形にしたい」と考え、その一環として福利厚生の充実を検討します。経営者としては、給与ではない形で社員にプレゼントをしたいところですが、「税務の壁」が立ちはだかり、思うようにプレゼントしたりすることができません。
税務上のルールにのっとって社員にプレゼントをすれば福利厚生費などとして損金に算入できますが、そうでなければ社員等(役員を含む。以下、同様)の給与または賞与(以下「給与等」)となって給与課税しなければなりません。
では、福利厚生費と給与の境界線はどこにあるのでしょうか。ケース・バイ・ケースで一概には言えませんが、この記事でいくつかの判断基準を紹介するので参考にしてください。
2 損金に算入できる福利厚生費の3つの要件
まず、福利厚生費について説明します。実は福利厚生費に関する税務上の明確な定義はありません。ただし、福利厚生費を損金に算入するには、次の要件を全て満たす必要があります。逆にいえば、これらの要件を満たさない社員へのプレゼントは給与課税されます。
- 会社の全社員(役員を含む。以下「社員等」)を対象とするものであること
- 支出する金額がおおむね一律で費用が社会通念上(常識的に)高額ではなく、通常要する費用として一般的な範囲内であること
- 原則、現金支給ではないこと
全ての社員等にとって機会が平等である必要があるので、特定の社員だけを対象にしたプレゼントは福利厚生費にはなりません。金額の基準は「社会通念上」や「通常要する費用として一般的な範囲内」と曖昧ですが、極端に高額にならないようにしましょう。国税庁のタックスアンサーや過去の判例なども参考になります。また、現金支給によるプレゼントは認められず、商品券も基本的にダメです。
以上がこの記事における福利厚生費の説明ですが、もっと詳しく知りたい方は次の記事を読んでみてください。
3 社員へのプレゼントは給与課税が基本。例外は?
所得税の基本的な考え方は、社員へのプレゼントなど福利厚生の支出は、社員等への給与等として課税するというものです。
ただし、前述した3つの判断基準に基づき、社員等にとって所得税が非課税となるものや、一部のみが課税対象となるような例外的なケースもあります。例外的なものに該当するかどうかはケース・バイ・ケースで難しい面があるため、以下でいくつかの例を紹介します。
1)社員旅行を実施する場合
社員旅行の費用として会社が負担した金額が、福利厚生費になるか否かの判断基準は次の通りです。これを満たせば、福利厚生費や旅費交通費として損金に算入できます。
- 旅行の企画、目的、社員の費用負担割合などを全体的に考慮して、一般的にレクリエーション旅行と認められるものであること
- 国内旅行なら4泊5日以内、海外旅行なら海外での滞在日数が4泊5日以内であること
- 参加割合が全体の人数の50%以上であること
- 不参加者に旅行相当額などの金銭の支給をしていないこと
なお、社員等に対する日ごろの慰安と業務研修を兼ねて「研修旅行」とするケースがあります。この場合は、業務を行うために直接必要な部分の費用だけを福利厚生費として損金に算入できます。それ以外の費用は給与として所得税が課税されます。
国税庁タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2)社員等に誕生日プレゼントを贈る場合
社員等の誕生日に社内規程で定めるプレゼントを贈る場合、誕生日ケーキや花束など社会的な慣習として広く一般的に贈られるプレゼントであれば、福利厚生費として損金に算入できます。
ただし、祝い金(商品券などのように換価が容易なものを含む)を支給する場合や、高額なものをプレゼントする場合は、給与として課税されます。
国税庁タックスアンサー「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
3)永年勤続者に記念品を贈呈する場合
永年勤続者に、記念品として物品、旅行券、観劇券などを支給した場合の費用は、次の3つの要件を満たしていれば、福利厚生費として損金に算入できます。
- その人の勤続年数や地位などに照らし、一般的に相当な金額であること
- その人の勤続年数がおおむね10年以上であること
- 同じ人を2回以上表彰する場合、前回からおおむね5年以上がたっていること
記念品ではなく金銭(商品券などのように換価が容易なものを含む)を支給する場合や、本人が自由に記念品を選択できる場合は、金額の多少に関わらず、給与として課税されます。
国税庁タックスアンサー「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
4)社員の資格取得費用を支給する場合
社員が職務に直接必要な技術や知識を習得したり、免許や資格を取得したりするための費用は、次の2つの要件を満たしていれば、福利厚生費や研修費として損金に算入できます。
- 通常の給与に加算して支給する費用であること
- 法人の場合、「役員の学資に充てるため支給する費用」「役員や社員の親族などの学資に充てるために支給する費用」のいずれにも該当しないこと
ただし、税理士や中小企業診断士などの一身専属的な資格については、役員や社員の職務に「直接必要な」資格とはいえないことがあるので注意が必要です。
国税庁タックスアンサー「No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
4 経理処理の留意点
会社の処理としては、
給与課税されなければ福利厚生費などとして処理をし、給与課税されるのならば給与等と同様に源泉徴収する
ことになります。
注意が必要なのは、役員へのプレゼントなどが給与等に該当する場合です。役員報酬のうち「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれにも該当しないものは損金に算入できません。また、これらに該当するものでも、不相当に高額な部分の金額は損金に算入できません。
そのため、例えば、定期同額給与の役員に給与等に該当する高額な誕生日プレゼントを贈ってしまうと、定期同額給与の要件に該当しなくなります。その場合、誕生日プレゼントの分が損金不算入となり、法人税が課税されてしまいます。
なお、役員報酬については次の記事で詳しく説明しています。
5 事前確認が大切
ここまで紹介したように、福利厚生費用の税務上の判断は簡単ではありません。また、福利厚生制度に関する社内規程を整えたり、これらの支出についての客観的な確認資料(証拠資料)を残しておいたりすることも大切です。そのため福利厚生を見直すときには、顧問税理士や税務署などと相談しながら進めていきましょう。
以上
(監修 税理士 石田和也)
※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2024年3月18日時点のものであり、将来変更される可能性があります。
※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。上記内容に関するお問い合わせなどは、お手数ですが下記の電子メールアドレスあてにご連絡をお願いいたします。
【電子メールでのお問い合わせ先】
inquiry01@jim.jp
(株式会社日本情報マートが、皆様からのお問い合わせを承ります。なお、株式会社日本情報マートの会社概要は、ウェブサイト https://www.jim.jp/company/をご覧ください)
ご回答は平日午前10:00~18:00とさせていただいておりますので、ご了承ください。